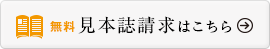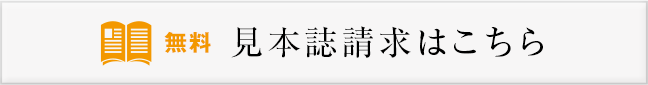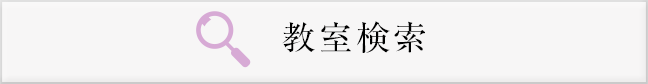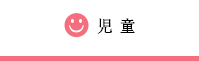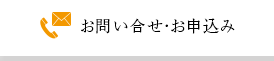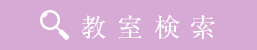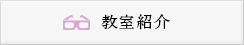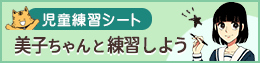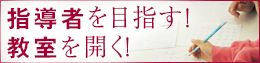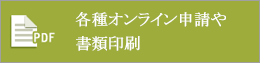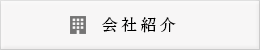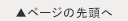第39回日本書道学院展が開催されました
2017年11月17日
11月10日(金)~16日(木)に、東京都美術館にて第39回日本書道学院展を開催し、無事終えることができました。
会期中、ご来場ご高覧いただいた皆様、授賞式・祝賀会にご参加の皆様、また本展開催に際しご協力いただきました先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。





11月10日(金)作品解説
審査員の先生方による作品解説が行われました。
上位受賞作品と審査員の先生方のお作品について解説していただきました。




11月10日(金)授賞式・祝賀会
上野精養軒にて開催いたしました。全国各地から多くの方にご出席いただきました。
受賞されました皆様おめでとうございます。今後ますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。


▲大賞受賞者の方々

▲神納耕石さんによる受賞者代表スピーチ

▲中国大使館 賀怡蘭先生と石川芳雲学院長
11月11日(土)席上揮毫①、11月14日(火)席上揮毫②
審査員の先生方による席上揮毫が行われました。大勢の方に、間近で先生方の筆や墨の使い方をご覧いただきました。
今回展は2日間開催いたしました。








11月12日(日)三部(アンダー23)授賞式、スカラシップ認定式
第39回日本書道学院三部授賞式ならびに平成30年度スカラシップ認定式をを執り行いました。
先生方からの激励の言葉に、みなさん熱心に聞き入っておられました。これからますます書の道を極めていっていただきたいと思います。



11月12日(日)ワークショップ「戌年の年賀状を書く」
二宮奇龍副学院長をはじめ常任理事、理事の先生方に年賀状を書くポイントをレッスンしていただきました。
特別講師に露﨑玄峯先生をお迎えし、消しゴム印の実演をしていただきました。



審査員の先生方による席上揮毫が行われました。
今回の展覧会の上位受賞者の作品は、月刊誌「書の光」2月号に掲載されます。
見応えたっぷりの特集号です。ぜひご覧ください。
第39回 日本書道学院展 開催中
2017年11月9日
◆会期:平成29年11月10日(金)~16日(木)
◆会場:東京都美術館2階第3・4展示室
●作品解説 11月10日(金)午前11時~
●席上揮毫 11月11日(土)午後2時~
●ワークショップ
「戌年の年賀状を書く」 11月12日(日)午後2時~
●席上揮毫② 11月14日(火)午後2時~
大阪・名古屋でペンかな講習会開催 !!
2017年10月30日
10/28(土)大阪、10/29(日)名古屋でペン習字かな講習会を開催しました。

「動きを感じさせる文字の書き方」の講義とワークショップと「美しく魅せる作品の構成について」他、秋の昇格試験対策や、競書課題11月号の作品制作、展覧会に向けての作品づくりなど、盛りだくさんの内容でした。

講義と作品制作実習と個別添削で作品づくりのポイントがよくわかります。

講師の先生から参加者全員に作品のプレゼントもありました。

見学の方も歓迎いたします。詳しくは,本部・事務局まで電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
第二回百合堂同門師生書法展
2017年10月30日
2017年10月27日 中国上海の劉海粟美術館分館において
日本書道学院 顧問王偉平先生の社中展『第二回百合堂同門師生書法展』が
開催され、その開幕式に石川芳雲学院長がご招待を受け、参列されました。
祝辞を述べられる石川芳雲学院長

テープカット

百合堂の皆様

ご来賓の皆様

会場風景1

会場風景1

2泊3日の強行軍でしたが、中身の濃い訪中でした。
帰国の日には、早朝にもかかわらず、ご門下の皆様にお見送りいただきました。
王偉平先生、ご婦人の唐月珍女士、百合堂の皆様、本当にありがとうございました。謝々。

10/22(日)ペン習字《かな講習会》が行われました
2017年10月23日
愛知よりご参加の方から感想をいただきましたので、ご紹介させていただきます。

東京・早稲田教室での「かな」講習会に参加させていただきました。今回は、講習会参加の感想を書かせていただきます。
「かな」と規定部との違いから始まり、「し」を書く時の書き方、考え方や美しく見せるためのかなの変化のさせ方、連綿についての考え方など盛りだくさんの内容でした。
座学の時でも軽いワークがあり、ひとりひとり先生自ら受講生の前に行かれ、一言ポイントを指摘していただけ、それを他の受講生が聞き耳を立てながら、ワークを楽しむというスタイルが気に入っています。
昼食は、ちらし寿司弁当。散らし書きが、上達したい受講生にちらし弁当とは。スタッフの粋な計らいにも頭が下がります。
昼食をはさんで、二度行われる目玉の添削は、なぜこの変体かなを使うのか、なぜここに文字を配置したらいいのか、枦元先生から丁寧な添削をしていただき、台風を気にしながらの上京も「来てよかった」感が勝り、「かな」への情熱も高くなりました。
そもそも「毎月のかな部の競書券を捨てるのが惜しい」というしょうもない理由からかなを始めたのですが、今では古筆の本を買ったり、いただいた枦元先生の作品(講習会参加者への特典として毎回ひとりずつ、手書きの俳句作品やコピーではありますが、しばしば試験課題の参考手本がいただけます)を鑑賞するようになりました。
今回の講習会で最も印象に残ったのは、「かな創作の時に余白の美は、とても大切だと思うが、余白をどういう風に決めているのか」という質問に対し「それは、(美しくなるように)考えている、そういう時間が楽しいのですよ。」という返答が返ってきたことでした。
今までは、創作は、時間も手間もかかって面倒だ、できれば手本を手にしたい、という思いが強かったので、「そうじゃない、一流の人は、その時間と手間を楽しんでいるんだ!」とすごく納得できました。他から「楽しめ!」と言われて楽しめるものではありませんが、徐々に「楽しむ心」が湧いてきそうな予感は、ありますので、その心に従ってかなに取り組んでいきたいと思います。
台風による新幹線運休が気になり、少し早めに退席いたしましたが、「講習会」は、独習者にはなくてはならないものだと痛感しており、また、機会があればぜひ参加させていただきたいと思います。ありがとうございました。
※全国各地の講習会では、初心者の方から経験者の方まで幅広くご指導いたします。
見学も随時できます。事務局までお電話かメールで連絡下さい。